改正建設業法施行に向けた労務費基準の動向 -第7・8回労務費に関するWG-

国土交通省の中央建設業審議会は、2025年5月8日に「第7回 労務費の基準に関するワーキンググループ(以下、WG)」、2025年6月3日に「第8回 労務費の基準に関するWG」を開催しました。
※「労務費の基準に関するWG」は改正建設業法(令和6年9月施行)の内容を踏まえ、建設工事の労務費に関する基準作成を目的としております。
当日の配布資料についても公開がされています。(第7回は配布資料なし)
※配布資料:第8回 労務費の基準に関するWG 配付資料
各回のアジェンダは以下となります。
<第7回>
(1)実効性確保策により中長期的に目指すベき将来像について
(2)実効性確保策(出口)に関する方向性について
(3)実効性確保策(公共工事の出口)に関する方向性について
<第8回>
(1)労務費の基準の実効性確保策について
(2)労務費の基準の作成について
<これまでの議論内容(第1〜6回 WGの内容)>
※詳細については過去の記事をご参照ください。
・第1回 労務費の基準に関するWGについて
・第2回 労務費の基準に関するWGについて
・第3回 労務費の基準に関するWGについて
・第4回 労務費の基準に関するWGについて
・第5回 労務費の基準に関するWGについて
・第6回 労務費の基準に関するWGについて
<第7回 WGの内容>
第7回のWGでは実効性確保策に関する議論として、中長期的なビジョン、公共・民間工事共通の取り組み、そして公共工事特有の取り組みという3つの主要な柱に沿って進められました。
実効性確保策が目指す中長期的な将来像については、事務局が作成した案をもとに議論が行われ、公共・民間工事に共通する「出口」の実効性を確保するため、以下の2点が話し合われました。
・賃金確認の方法:発注者、元請け、下請けそれぞれの責任を明確にした上で、デジタル技術を活用した効率的な賃金確認のあり方が検討されました。
・コミットメント制度:これまでの委員の意見を反映させ、制度の具体的な運用方法について議論されました。
公共工事特有の取り組みとして、賃金水準の設定方法と支払いの確認方法に関する案が提示され、今後の方向性について話し合いが行われました。
<第8回 WGの内容>
⒈労務費の基準の実効性確保策について
建設業界の健全な競争環境を築き、技能者の処遇改善を実現するための具体的な施策が話し合われました。特に、「入口(契約段階)」と「出口(賃金支払い段階)」の両面から、労務費が適正に確保・支払われるための仕組みについて、以下の点が検討されました。
<入口(契約段階)での議論>
・見積もりにおける労務費・必要経費の明示
改正建設業法に基づき、労務費に加え、法定福利費、安全衛生経費、建退共掛金などの必要経費を内訳として見積書に明記することが検討されました。これらの経費が不当に削減されることを防ぎ、見積りの透明化を促す狙いがあります。
・優良事業者の「見える化」
適正な見積もりを行う事業者を市場で評価する『自主宣言制度』の導入が検討されました。宣言した企業はロゴマークの使用や、経営事項審査での加点といった優遇措置を受けられるようになります。中小企業と大手企業が公平に認証を受けられるよう、制度設計に配慮すべきとの意見が出されました。
・建設Gメンの活用と関係機関との連携
建設Gメンがダンピングや不当な取引を調査する体制が議論されました。賃金問題だけでなく、建設業法全般にわたる問題も視野に入れ、労働基準監督署などとの連携を強化することで、より効果的な調査体制を築くことが提案されました。
・公共工事におけるダンピング対策:
2025年12月以降、公共工事の入札参加者には入札金額内訳書の提出が義務化されます。これにより、発注者は労務費が不当に低いかどうかを確認し、ダンピングが疑われる場合にはGメンによる調査につなげる方針です。ダンピング業者を確実に排除できるよう、入札の段階で受注させない仕組みを構築すべきだとの意見も出ました。
<出口(賃金支払い段階)での議論>
確保された労務費が、実際に技能者の賃金として支払われることを確認する仕組みについて、以下の点が議論されました。
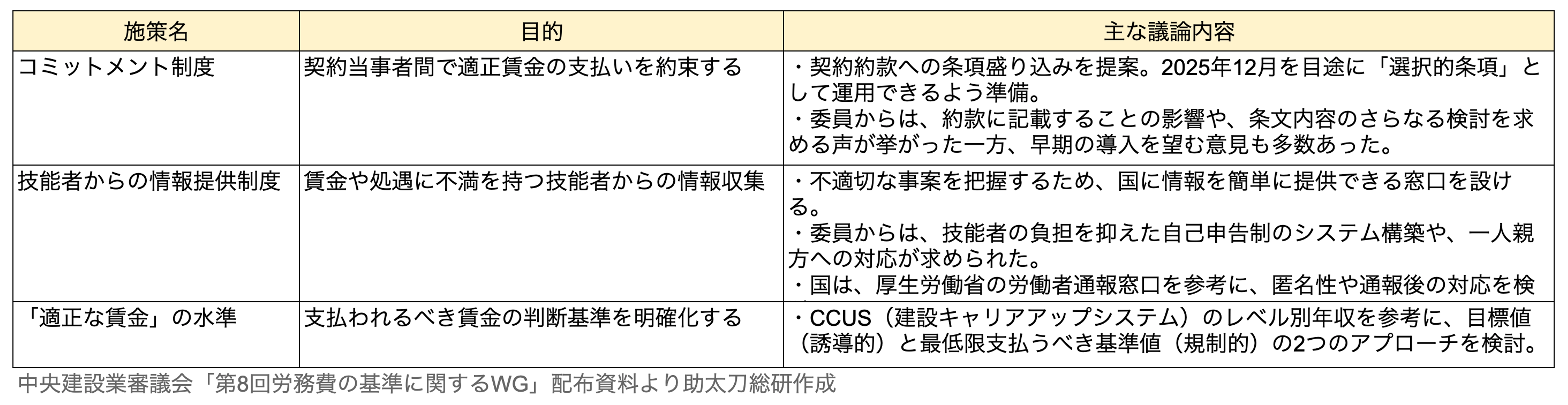
2. 労務費の基準の作成について
労務費の基準作成について、職種別の意見交換を踏まえた修正案が提示され、主に以下の2点が議論されました。
・都道府県別の基準について
事務局は、公共取引との整合性を考慮し、設計労務単価と同様に労務費の基準を原則として都道府県別に設定することを提案しました。
しかし、これに対し委員からは「地域間格差を助長する」との懸念が示され、全国一律の基準を望む意見も出されました。結果として、この点については合意に至らず、今後の再議論が確認されております。
・設計労務単価の活用について
労務費の基準のベースとして設計労務単価を用いることについても議論されました。委員からは「政策的な基準なのに実態調査に基づく単価で良いのか」という根本的な疑問が提起されました。
一方で、現時点で代替となる適切な指標がないことから、まずはこれを活用して議論を進めるべきだという意見も出ました。さらに、建設業の担い手確保という喫緊の課題を解決するため、設計労務単価の1.5倍を目指すといった具体的な提案もなされました。
まとめ
今回の議論では、労務費の実効性確保策については概ね方向性が定まりましたが、基準の作成方針については、引き続き議論が必要な論点が浮き彫りとなりました。今年の12月の施工に向けて今後の協議で、これらの課題についてさらに検討を深めていくことになります。

助太刀総研 運営事務局
Sukedachi Research Institute
